前回の『私のマトカ』に続き、今回も読書を通じたフィンランド旅へ。選んだ作品は『ほんとはかわいくないフィンランド』(2020年/幻冬舎)です。
IT業界の会社員兼ライターとして東京でバリバリ働いていた著者の芹澤桂さんが、フィンランド人との結婚を機にヘルシンキへ移住し、現地で感じたギャップやリアルな暮らしぶりを綴った本著。
同作のヒットを受け、2021年に『やっぱりかわいくないフィンランド』、2022年に『意地でも旅するフィンランド』、2023年に『それでもしあわせフィンランド』とコンスタントに続編もお目見えしています。
生活を楽しむ知恵
独身時代にもヨーロッパ5か国を周遊する旅でヘルシンキを訪れていた芹澤さん。お土産に北欧雑貨を買おうと張り切って街を散策するも、「かわいいものがどうも見つからない。そもそも雑貨屋さんというものがあまりない」と、最初のイメージはイマイチだったみたいです。
そんなヘルシンキは住めば都か、はたまた地獄か。結論から言うと、芹澤さんの文章には終始フィンランド愛がダダ漏れ。
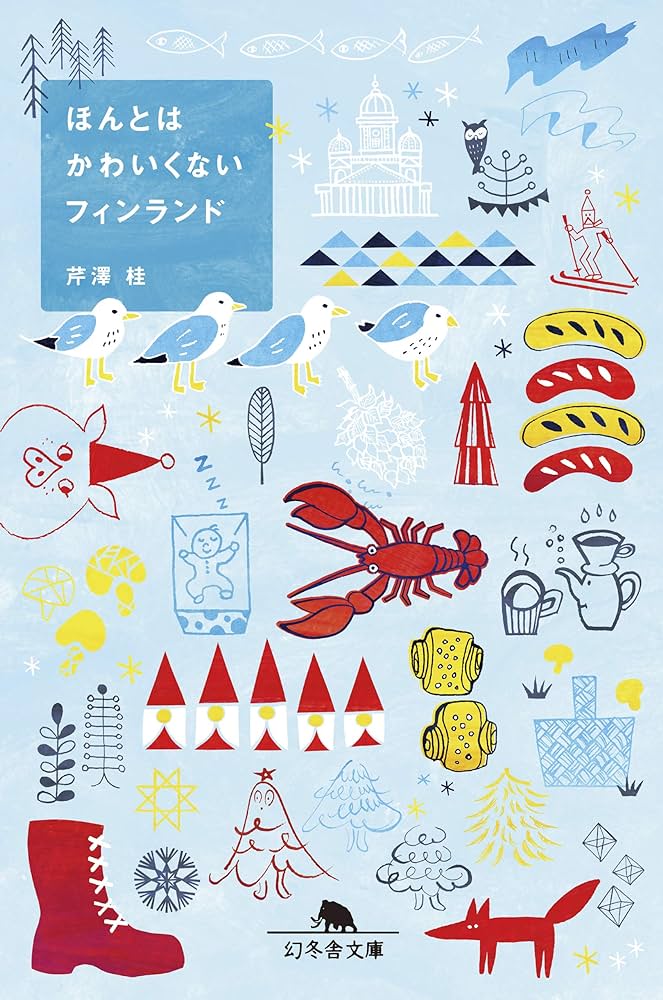
サンタクロースの助手も森や湖やサウナに棲む妖精もみんなオジサンだったり、公に推奨されている食事の回数が1日5回だったり、『私のマトカ』でも詳しく触れられている悪評高きサルミアッキだったり、確かにあまりかわいくない話題だらけ。
ヨーロッパのなかでも物価の高い国だけに倹約家が多く、とりわけファッションに関しては「おしゃれでもなければかわいいでもない」と完全に諦めモードです。
しかし、物価の高さ然り、寒く厳しい冬然り、普通に考えたらネガティヴに捉えてしまいそうなところを、あれこれ工夫して楽しむのがフィンランド流。
その姿勢に対する著者の驚きと感動が随所で伝わってきますし、おそらくそうした工夫の部分に同国の幸福度の高さの秘訣が隠されているのでしょう(※フィンランドは幸福度の高い国ランキングの2024年版でも7年連続1位を記録)。

極寒の地で育まれたサウナ文化は言わずもがな、倹約志向についてはフリーマーケットを紹介するシーンが印象的。フリーと言っても蚤の市のFleaではなく、無料のFree。小さくなった子ども服を寄付する代わりに、欲しい服を持ち帰れるシステムらしいです。
そこには「ものは大事に寿命が来るまで使う、寿命を待てなければ次の使い手を探す」といった考えが根底にあるとか。
長らく大量生産・大量消費・大量廃棄社会を続けてきた日本。ようやく世の中全体の風潮が変わりつつあるものの、私ももう少し踏み込んで「ものを大事にすること」「ものの寿命」の意味と向き合わなきゃいけないなと感じました。
世界一お母さんにやさしい国!?
全編を通して『ほんとはかわいくないフィンランド』は肩肘張らずに読めるエッセイです。でも、先の倹約志向と併せ、日本の抱える社会課題と向き合うきっかけをくれた箇所がありました。
本著は出産や子育てにまつわるエピソードにかなりの紙幅が割かれています。フィンランドはジェンダーギャップ指数で常に上位をキープしているほか、Save the Children発表の『World's Mothers report』でも世界一お母さんにやさしい国に選出されています。

残念ながら日本は足元にも及びません。だけど、意外にも育児休暇に伴う制度は、細々した違いはあるにせよ、思ったほど大差がないように見えました。
本書によると、フィンランドの産休・育休は4か月間(男性のみに与えられる育休は9週間)。日本は3か月間。
また、フィンランドも日本も両親共に育休の取得は可能ですが、フィンランドは片側の親だけが育児手当を取得でき、日本は両親どちらも手当を取得できるうえに受取額も高いです(※物価はフィンランドのほうが高いのに)。
権利と義務

さらに、終盤に設けられた『優しいは厳しい』なる章で、結婚した途端に無職となった芹澤さんは、こんなふうに綴られていました。
もし子供を授かっても育休中じゃなければ無職。働かずに子供の面倒を家で見る場合、国とヘルシンキの場合は市から手当が出るけれど、「専業主婦」や「子供の面倒を家で見ている」という枠は公式にはなく、ステータスは無職のままだ。
ついでに扶養制度もない。
夫は会社員なので会社の福利厚生サービスにより、ちょっとした風邪や捻挫でもすぐに私立病院にかかれ医療費は会社が負担してくれる。
しかし妻である私はその恩恵を受けることができない。勤めない限り、もしくは任意で一般の保険に加入しない限りは、病気になっても公共の診療所を訪れることになる。
公共なら安そうだしいいじゃないという声が聞こえてきそうだけれど、診療所は専門病院ではなくあくまでも内科のような存在なので、基本的な診断しかできず風邪程度じゃ見ない、何もしないのが現実だ。
それゆえ我が家のように一家庭内でも受けられる医療サービスに格差が生じている。
産休・育休後に復職する女性の割合が年々増えてきたとはいえ、日本では育休・産休明けの離職率がしばしば問題になっています。
私の回りにも休業手当をもらってさっさと退職した人、立て続けに2人目を出産して産休・育休を延長した末に気持ち的な理由で復帰できなくなった人、昇進のオファーを断って時短勤務の継続を希望し、とりあえず福利厚生の旨みを享受せんと会社に居座っている人がいます。
彼女たちのほとんどが大企業に就職した、いわゆるエリート人材。ひょっとして現在の日本は制度作りに意識が向かいすぎ、女性を甘やかしてしまっているのかも。ついでに、何が悲惨かって、民間会社や関係省庁の首脳陣が男性中心のせいか、せっかく整備した優遇制度もイイ感じに機能せず、当事者からは不評な点。

もちろん、フィンランドのやり方をそのまま日本に適用しても上手く回るとは考え難いですし、そもそも私は専業主婦肯定派です。日本の伝統的な家父長制にもメリットは多い気がして、何でもかんでも男女平等が素晴らしいとは思いません。いろいろな選択肢があってほしいです。
ただし、国や企業が女性活躍を推進したいなら、優しさと同時に厳しさも与えないと。特に企業はボランティアでやっているわけじゃなく、それゆえに、女性側は権利を主張する前に義務を果たすべき……と、フィンランドの実態を知ってぼんやり考えていました。
男女平等でお母さんにやさしい国の現実は決して甘くなかったです。結局、幸福度を高めるためには、何事も人任せにせず、自分で努力し、チャンスを掴みにいくしかないって話なんですかね。
※記事内の画像はフリー素材を使用しています。本著とは直接関係ありません。
ランキング参加中。ぽちっとしていただけたら嬉しいです。